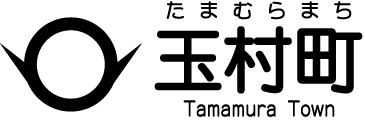公開日 2014年09月18日
更新日 2024年04月01日
担当課
- 役場1階税務課
固定資産税とは
- 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人
- 固定資産税を納める人は、原則としてその固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
- 土地
- 登記簿に所有者として登記されている人又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
- 家屋
- 登記簿に所有者として登記されている人又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
- 償却資産
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額算定のあらまし
- 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- (1)固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- ↓
- (2)課税標準額(土地・家屋・償却資産の合計額。千円未満切捨て)×税率=税額(百円未満切捨て)
- ↓
- (3)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
税率
- 固定資産税の税率は、1.4%です。
免税点
- 固定資産税には、次の通り免税点が設定されており、それぞれ課税標準額が記載されている金額未満であれば、その分の固定資産税はかかりません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
課税のしくみ
1. 土地に対する課税
-
評価のしくみ
- 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
-
地目
- 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
2.家屋に対する課税
- 家屋の認定は次の3つの条件を満たすものです。
- 基礎などで土地に定着している。(土地定着性)
- 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し独立して風雨をしのげ、外界から遮断された空間を持っている。(外気遮断性)
- 居住、作業、貯蔵等の用途に供しえる状態にあるもの。(用途性)
-
評価のしくみ
- 建物が新築されますと、主として、町の職員(評価員・評価補助員)が直接お宅へお伺いして家屋の構造及び各部分の使用材料や仕上げ状況等を調査します。
-
評価額の算出方法は、次の式により算出されます。
- 評価額=評点数×評点1点当たりの価額
評点数=再建築費評点数×経年減点補正率
評点1点当たりの価額=1円×物価水準による補正率×設計管理費による補正率
再建築費評点数= 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率=家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
3. 償却資産に対する課税
- 固定資産税における償却資産とは、土地と家屋以外の、事業のために用いることができる、有形の減価償却資産のことです。
- 償却資産を所有する人(個人または法人)は、地方税法第383条の規定により、毎年、1月1日現在の償却資産の所有状況について申告してください。
- 町では、その申告内容等に基づいて、毎年度、評価額及び課税標準額を算出します。
- 地方税法第353条の規定に基づき、所有資産について質問や調査を行うことがあります。
- 【申告が必要な人】
- 会社(工場・店舗・事務所など)・賃貸アパート・賃貸駐車場・農業などを経営したり、太陽光発電設備での売電などをしたりしている個人や法人で、その事業のための構築物、機械、器具・備品などを所有している人
- 【申告が必要な償却資産の例(主なもの)】
| 共 通 | 外構工事(舗装、門・塀・フェンス、緑化施設など)、外灯、看板、パソコン、コピー機、エアコン(ビルトインタイプでないもの)、レジスター、テレビ、応接セット、ロッカー、キャビネットなど |
| 運送業 | フォークリフト(小型特殊自動車でないもの)など |
| 工場・製造業 | 各種製品製造設備、受変電設備、構内舗装、太陽光発電設備(※)、フォークリフト(小型特殊自動車でないもの)など |
| 印 刷 業 | 製版機および印刷機、断裁機など |
| 建 設 業 | ブルドーザー、パワーショベル、大型特殊自動車、発電機、ポンプなど |
| 農 業 | 農機具、ビニールハウス、大型特殊自動車、舗装・コンクリート施工 など |
| パチンコ店、ゲームセンター |
パチンコ店、ゲームセンター |
| 飲 食 店 | テーブル、椅子、厨房設備、冷蔵庫、音響設備など |
| 小 売 店 | 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫、厨房設備、自動販売機など |
| 理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど |
| 医院、歯科医院 | 医療機器(ベッド、レントゲン装置、手術機器)など |
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など |
| アパート経営 | フェンス、自転車置場、太陽光発電設備(※)など |
| ガソリンスタンド |
洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、地下タンク、照明設備など |
| 売 電 業 | 太陽光発電設備(※) ただし、個人住宅用で、かつ出力10kw未満のものは対象外 |
- (※)太陽光発電設備には、パネル本体、パワーコンディショナ、杭架台、運搬・設置工事費、敷地の舗装・外構工事費などが含まれます。また、種類別明細書へは、耐用年数の異なるものは分けて記載してください。
- 【申告不要のもの】
- 事業用として所有していても、以下に該当するものは、償却資産の申告(課税)対象外です。
- 1.土地または家屋として課税されている資産
- 2.自動車税、軽自動車税として課税対象の車両
- 3.無形固定資産、無形減価償却資産
- 4.耐用年数1年未満の償却資産又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上、一時に損金算入したもの(消耗品など)
- 5.取得価格が20万円未満のもので3年間で一括して均等償却するもの
- 6.パネルが屋根材に埋め込まれ(または屋根材そのもので)、家屋として評価課税されている太陽光発電設備
- 7.個人住宅用で、かつ出力10kw未満の太陽光発電設備
- 【申告の方法】
- 毎年1月1日時点の所有状況を、エルタックス(eLTAX)で電子申告するか、申告書及び種類別明細書の書面にご記入の上ご提出ください。
- 種類別明細書に記載する際は、それぞれの取得価格、取得時期、耐用年数、数量をよくご確認ください。また、店舗・会社所在地等と異なる場所に償却資産が存在する場合(例:野立の太陽光発電設備)は、「資産の名称等」欄に、資産の名称のほか、所在地も併記してください。
- 申告書には、所有者情報のほか、種類別明細書を集計し、各資産の種類別合計額も記載してください。
- 記入用紙が必要な人は、お電話等でお申し出ください。
- 書面を提出する人で、申告の受付確認が必要な場合は、申告書及び種類別明細書の提出用と控用、返信用封筒(切手も必要)をご提出いただければ、控用に受付印を押印し返送いたします。
- ※※※ 申告期限は、毎年1月末日です。 ※※※
Q&A
Q 固定資産の評価替えとは何ですか?
- A 評価替えとは、土地・家屋の価格の見直しをいいます。 固定資産税は、固定資産の「適正な時価」をもとに課税することが法律で定められているので、定期的に土地・家屋の価格の見直しを行なっています。ただし、膨大な量の土地・家屋を毎年評価替えすることは実務上不可能であることなどから、評価替えは3年に1度行い、それ以外の年度は原則として価格を据え置く制度がとられています。ただし、土地については地価の下落により価格を据え置くことが適当でないと町長が判断したときは、評価替え以外の年度であっても、簡易な方法で価格の修正を行なうことになっています。
Q 固定資産税には、「閲覧」と「縦覧」という制度があると聞きましたが、これはどのようなものでしょうか?
- A 閲覧制度は、納税義務者等の方に、固定資産税課税台帳に記載された課税内容を確認していただくものです。 縦覧制度は、納税者が自己の土地や家屋の価格が適正かどうかを、土地・家屋価格等縦覧帳簿で、他の土地や家屋の評価額と比較して、確認できる制度です。なお、玉村町の縦覧期間は、毎年4月1日から第1期納期限日までです。
Q 土地と家屋を売却したのですが、固定資産税は誰に課税されますか?
- A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)の登記簿(登記されていない場合は課税台帳)に記載されている所有者に課税されます。その所有者に1年分の固定資産税を支払う義務があります。
Q 地価が下落しているのになぜ土地の税額が上がるのでしょうか?
- A 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平という観点から観ると問題があることから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を図る措置が講じられています。具体的には、この負担水準が高い土地は税額を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税額を引き上げていくしくみです。玉村町の土地はほとんどがこの負担水準が低い土地に該当していますので、税額がゆるやかに上昇しています。
Q 昨年、住宅を取り壊したのに、税金が高くなったのはどうして?
- A 住宅が建っている土地には、住宅用地に対する課税標準の特例が設けられていて、税額が低く抑えられています。
この特例は、毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用されているものに限ります。つまり、住宅を取り壊したことにより、家屋については課税されなくなりましたが、土地については住宅用地の特例が受けられなくなったので、その特例による減額分の方が家屋の課税分より大きかったので、全体として高くなったということです。
Q 住宅を新築して4年目に、固定資産税額が高くなるのはなぜ?
- A 新築の住宅に対しては、住宅建築の促進を図るため、固定資産税を軽減する措置があります。一定の面積と価格要件を満たせば、新たに課税されることとなった年度から、通常3年間(5年間の場合有り)、床面積120平方メートル分の固定資産税が、「2分の1」に軽減されます。4年目から本来の税額に戻ったので、税額が高くなったのです。
Q 住宅を建てて年数が経っていますが、家屋の税額が下がりません。どうしてですか?
- A 家屋の評価額は、「再建築価格」と「経年減点補正率」を使って求めます。 「再建築価格」とは、評価の対象となった家屋と全く同じものを評価の時点において、新築した場合に必要とされる建築費です。
- 「経年減点補正率」とは、建築後の年数の経過に応じて生ずる減価をあらわしたものです。
- 3年に一度、評価の見直しを行いますが、家屋が古くなっても、現在の建築物価により再建築したものとして計算されるため、「再建築価格」には、建築物価の上昇が加味されます。建築当時からの「建築物価の上昇」が激しい場合(例えばバブル期など)には、建築後の家屋の経過年数に応じた経年減点補正率を掛けて求めた評価額が、前年度の評価額を上回ることがあります。
- ただし、その場合には、前年度の評価額に据え置くこととされています。このような理由で、住宅の固定資産税が下がらないという状況が出てきます。
関連リンク
【固定資産税共通】
【家屋】
【償却資産】
「先端設備等導入計画」の認定 ←該当する場合、課税標準の特例対象です。
この記事に関するお問い合わせ
税務課
住所:〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201
TEL:0270-64-7703
FAX:0270-65-2592