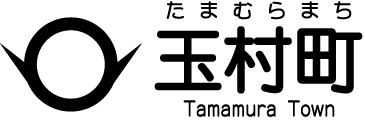公開日 2018年04月01日
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済み期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金額を受け取る「繰り上げ受給」や、65歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰り下げ受給」の制度があります。
障害基礎年金
国民年金加入期間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)に、初診日のある病気やけがで、法に定める障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日においての保険料納付要件が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
障害基礎年金の請求方法
①障害認定日による請求
障害認定日に障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により5年分です。
②事後重症による請求
障害認定日に障害の状態に該当しなかった人でも、その後症状が悪化し障害の状態になったときには、請求日の翌月分から年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
遺族基礎年金
国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格期間(納付・免除期間の合計)が25年以上ある人が死亡したときには、死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子で、子が18歳に達した年度末まで(障害年金の1級または2級の状態にある子の場合には20歳になるまで)遺族基礎年金が支給されます。ただし、死亡した人について、死亡日の前日において保険料納付済期間が国民年金加入期間のうち3分の2以上あることが必要です。(※令和8年3月末日までのときは、65歳未満であれば、死亡日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ受れらます。)
寡婦年金
受給資格期間(第1号被保険者期間の保険料納付・保険料免除期間の合計)が10年以上ある夫(かつ婚姻期間10年以上)が死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金の4分の3が受けられます。ただし、夫が障害基礎年金を受けたことや、妻が老齢基礎年金を受けているときは、受けられません。
死亡一時金
死亡月の前日において第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人が、年金を受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を収めた月数に応じて120,000円〜320,000円です。
関連ページ 日本年金機構(外部ページに移動します)